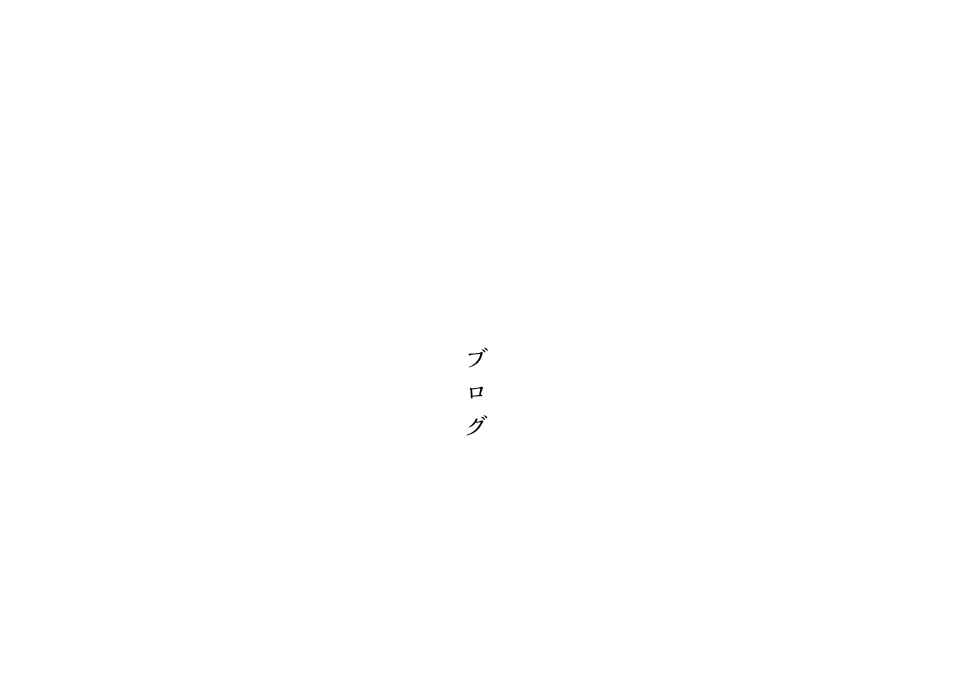古美術門運孔の更新担当の中西です
~真贋の彼方へ~
古美術の世界で避けて通れないテーマ――それが「真贋(しんがん)」です。
本物か、偽物か。
それをどう見極めるかは、長年の経験と感性が試される瞬間でもあります。
しかし、本当の“本物”とは、単に真作であることだけを意味しません。
そこには、作品に宿る「精神性」こそが問われるのです。
⚖️ 真贋とは何か
古美術の真贋判定は、時に曖昧で、答えがひとつではありません。
作家本人が手を入れたのか、工房の弟子が制作したのか、あるいは後年の模倣か。
たとえ後世の作でも、その作品が“時代の美意識”を正確に継承していれば、
それは「偽物」ではなく「文化の継承」として価値を持ちます。
つまり、“本物”とは単に「オリジナル」ではなく、
**「精神を受け継いだもの」**をも指すのです。
それを理解しているかどうかが、古美術商の力量と誇りを分けます。
鑑定の現場で求められる洞察力
実際の鑑定では、以下のような要素を総合的に見極めます。
-
素材の質感(陶磁器の釉薬、紙の繊維、木材の年輪)
-
技法の特徴(筆跡、彫り跡、焼き色)
-
経年変化(汚れ方、光沢の深まり、金属の酸化具合)
-
来歴(誰の手を経たか、箱書き・添状などの証拠)
しかし、最終的な判断を下すのは“経験に裏打ちされた感覚”です。
数字やデータではなく、作品と対話する中で「これは生きている」と感じ取る力。
それが本当の意味での“鑑識眼”なのです
時代が作る価値
面白いことに、今“贋作”とされている作品が、
100年後には「その時代の模写として貴重」と評価されることもあります。
美術の価値は、時代によって変化する。
だからこそ、古美術商は“今”だけの判断で作品を切り捨てることをしません。
歴史の流れの中で、いつか正しく評価される日が来る――
そう信じて、一つひとつの作品と向き合うのです。
まとめ
真贋とは、単なる“白黒”ではなく、“文化の層”を読み解く作業。
古美術商は探偵であり、哲学者でもあります。
目の前の作品が何を語り、どんな時代を映しているのか――
その声に耳を傾けることこそが、「本物」を見抜く第一歩です✨